施設紹介
実験室・実習室の紹介
教育研究棟(磐上館)
 スポーツ健康科学部教育研究棟(磐上館)
スポーツ健康科学部教育研究棟(磐上館)
京田辺キャンパス内の広大な体育施設の中央に、スポーツ健康科学部の教育研究棟である磐上館(ばんじょうかん)が設置されています。磐上館内には、演習や初年次教育授業を行うことができる
「演習室」や、最新のスポーツ科学を学修することができる各種
「実験室」、またスポーツ健康科学の専門書やスポーツ雑誌が保管されている
「書庫」、フィットネスやダンスなどの身体運動が可能な
「多目的実習室」、大学院生の発表会などができる
「カンファレンスルーム」、学生の自習教室である
「ラーニングテリア」などを設けています。
公式YouTubeチャンネルでは動画で施設をご覧いただけます。
運動生理学実験室I
運動生理学実験室Ⅱ
 運動生理学実験室Ⅱ
運動生理学実験室Ⅱ
運動生理学実験室Ⅱには、生理・栄養学分野の代謝測定に関する装置類が配備されています。中でも特徴的なのはヒューマンカロリメーターと人工環境制御室という大型装置です。カロリメーターは世界最高水準の分析機器で構成され、対象者に室内で過ごしてもらうだけでエネルギー消費量を正確に測定できます。人工環境制御室では温湿度が厳格に制御され、低酸素環境を作り出すこともできるため、低酸素トレーニングのような実践的研究も行えます。この他、食品のカロリーなどを簡便な手続きで分析できる機器も導入されており、運動生理学実験室Ⅱは、身体に取り込まれるカロリーと体内で燃焼するカロリーを総合的に評価できる実験室となっています。
環境生理学実験室
 環境生理学実験室
環境生理学実験室
この実験室では、温度と湿度をコントロールできる人工的な室内空間で、真夏の環境や真冬の環境を構築できます。試合の場面で、寒い雨が降る中試合に出続け低体温症で途中棄権したり、熱中症で脱水状態となり途中棄権するといった選手をよくみかけます。このようなことが起こらないためのからだの温度調節について知ることができます。また、高地トレーニングのような低温・低酸素でのトレーニングを人工的に構築し、同志社オリジナルの低酸素トレーニングについて血液や呼吸調節、エネルギー代謝について調べます。さらに、高度をもっと上げて宇宙空間での生理機能について、tilt table や下半身陰圧負荷装置を用いて考えていきます。
運動制御実験室
トレーニング科学実験室1
トレーニング科学実験室2
 トレーニング科学実験室2
トレーニング科学実験室2
トレーニング科学実験室2では、体を構成する組織の形態的データ(体脂肪量、骨格筋量、体脂肪率など)、筋力・筋パワー、神経・筋機能を測定することができ、トレーニングの効果検証やコンディションの評価に利用することが可能です。この実験室に設置されている超音波診断装置では、皮下脂肪量や骨格筋量を高精度で計測できる上、筋線維の収縮動態を、リアルタイムに且つハイスピードで捉えることが可能であり、最先端の研究にも利用されます。また、様々な部位の最大筋力、筋パワー、筋持久力を測定できる等速性筋力計が設置されており、これに筋電計を組み合わせて神経・筋機能を統合的に分析することが可能です。
運動学実験室
体力科学実験室
スポーツ・バイオメカニクス実験室
スポーツ心理学実験室
スポーツ医学実験室
生化学実験室・分子生物学実験室
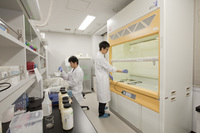 生化学実験室・分子生物学実験室
生化学実験室・分子生物学実験室
これらの実験室では、運動によって生体内で生じる応答やトレーニング効果が得られる仕組みを分子レベルで検討できる実験機器が揃っています。分子生物学は生化学に端を発する学問領域であることからこの2つの学問領域を明確に区別することは難しいのですが、生化学実験室では、対象組織内の標的分子が関わる生体内反応を試験管内 (in vitro) で再現して、代謝活性を測定したり、一過性の運動や継続的なトレーニングによるタンパク質や遺伝子の発現量の変化を測定したりすることが可能です。分子生物学実験室では、遺伝子の組替えを行うなどして標的とする分子を組織内で過剰に発現させたり、反対に発現量を抑制させたりしながら、運動という外的刺激が細胞内でどういった経路でどういった分子を介して、運動に対する応答やトレーニング効果を生じさせるのかについて検討することができます。
運動処方実験室
コンディショニングルーム
体育施設紹介

広大な敷地に展開するスポーツ施設
自分自身の競技力の向上を目指すも良し、コーチング力を高めるも良し。スポーツと健康の新時代を担うあなたのフィジカルとメンタルを試すフィールドはここにあります。
詳しい施設紹介をオフィシャルサイト内でご案内しています。
スポーツ施設紹介(オフィシャルサイト)
先端施設の活用について
トップアスリートの身体に秘められたメカニズムを探る研究!
一流選手の驚異的な身体能力は、どこから生まれてくるのでしょうか?こうした疑問を解くため、身体の内部からアスリートの秘密に迫る研究をしています。体の動きを生み出すのは筋肉です。筋肉は筋線維という細胞がたくさん集まってできていますが、この筋線維の束を超音波診断装置(エコー)により可視化し、その動きを分析しています。スポーツ健康科学部にある超音波装置は、1秒間に200枚の撮影も可能な、ハイスピードカメラならぬ「ハイスピードエコー」です。この装置を使って様々な動作の分析をしてみると、体の関節(肘や膝など)の動きと筋線維の動きは一致しないことがわかりました。例えば、関節は動いていなくても筋線維は短縮していることや、逆に関節はダイナミックに動いていても筋線維はほとんど動かないこともあります。これは、筋肉につながる腱がバネのように伸び縮みするからだと考えられています。そして、見た目の体の動きは同じであっても、筋線維の動きに個人の特徴があることもわかってきました。一流選手とそうでない選手の分かれ目は身体の内部の動きにあるのかもしれません。
このように、体の内部からの分析でアスリートの身体能力の秘密を解き明かし、さらに、それを身につけるための有効なトレーニング方法について研究しています。
二足での歩行・走行を生み出す 神経メカニズムの解明とトレーニングへの応用研究!
ヒトは二足による不安定な立位姿勢で歩いたり走ったりしています。その際、足の動かし方を強く意識することなしに、神経システムが多数の筋肉を適切なタイミングと強度で収縮させています。歩行の神経制御メカニズムについては、主に動物実験による研究成果を基にした理解となっていますが、二足によるヒトの歩行制御機構は四足歩行とは異なる可能性があり、ヒトでの研究が求められています。そのため、筋肉が収縮する際に生じる電位変化を皮膚上から計測することや痛みの生じない磁気・電気刺激を脳・神経系に与えることで、ヒトの歩行や走行の神経調節メカニズムを探究しています。なかでも歩行時の接地によって生じる荷重などの感覚情報が神経系の興奮性に及ぼす影響に着目しています。下半身を覆うドーム内部に空気圧をかけることで体重を20%まで軽減できる最新のトレッドミル装置が本学部に導入され、通常とは異なる体重条件下にて歩行制御メカニズムの基礎研究やより速く走るためのトレーニング方法の開発を目指した研究を進めています。また、脳卒中や脊髄損傷など神経系に障害が生じ歩行機能が損なわれた方の機能回復に向け、効率的な歩行トレーニング法を検討しています。




